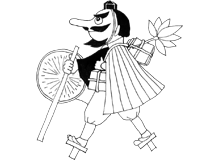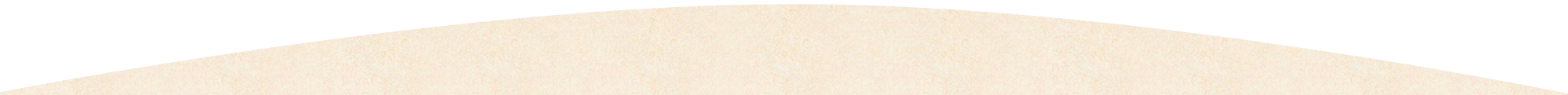この地区の行事
祭礼行事
- 春の祈年祭 3月第1日曜日
- 稲荷神社(初午) 3月第1日曜日
- 春の大祭 4月第2日曜日
- 二百十日祈願祭 9月第1日曜日
- 新嘗祭 12月第1日曜日
さわやかクラブ 65歳以上
- 奉仕作業
- 花壇の花植え替え 年2回
- 各文化財の保護活動 草刈り年2回
- 親睦旅行 年1回
- 総会及び親睦会 3月
ひまわりこども会
- どんど焼
- 新入生入学式
- こどもの日
- 七夕まつり
- 花火大会
- 日子連キャンプ
- 神明神社大祭 御神輿
- クリスマス
この地区の観光
本郷十三仏(じゅうさんぶつ)
横繩に、天保十三年(一八四二)に建立された十三仏石碑があります。
十三仏とは、死者の追善法事(初七日から三十三回忌まで)を行うとき、その年忌に配当された仏を拝むもので、日本独特の信仰といわれています。
本郷の十三仏碑には、上半分に十三の仏菩薩が浮彫りされ、下にと彫ってある立派なもので、右下方に阿彌陀三尊が追加されています。これは、建立三年後に村中安全を祈って追彫されたものです。
十三仏碑は市内にこの一基しかなく、昭和五十八年に市の文化財に指定されました。
なお、碑の前に元禄十三年(1700)に奉納された水鉢がありますが、これはこの北手にあった毘沙門堂から移したものです。同じ年、元禄十三年には本郷神明神社、常道神明神社、大山弘法堂にも水鉢が寄進されています。
神明神社と熊野杉(しんめいじんじゃとくまのすぎ)
神明神社の創建は寛文年(1669)で、天照大御神が祀られています。今の社殿は平成4年に改築されたものです。境内にある熊野杉は樹齢700年、周り7m、樹高60mで市の文化財に指定されています 。
本小高の弘法堂(おだかのこうぼうどう)
創建は享保年間(1720年代)、足元道知という僧が建立したと伝えられています。境内には51体もの石仏があり、他に芭蕉の句碑や石の塔があります。二列に並んでいる三十三所観音は特に立派です。